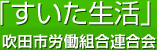
大阪空襲訴訟謝罪と賠償をもとめて
空襲傷害者――置き去りにされた民間の戦争被害者
その日、安野輝子さんは自宅で母親の帰りを待ちながら、弟や従兄弟たちと遊んでいた。1945年7月16日、すでに米軍は沖縄を陥落させていた。
沖縄から飛来する米軍戦闘機は、鹿児島の主要都市を連日のように空爆していた。
その日も空襲警報が鳴った。普段は警報が鳴ってから爆撃までにはしばらく時間があるので、防空壕へ逃げ込むことができていた。しかしこの日は違った。警報が鳴り止むか止まないかの内に、ドーンという爆音。気を失った。
「お姉ちゃん、痛いよ」弟の鳴き声で我に返る。あたりはヌルヌルとした血の海、弟や従兄弟たちが泣き叫んでいる。そのときは不思議と痛みさえ感じなかった。「弟たちをなんとかしなければ」。他人のことを気遣っていた。まさか自分の左足がなくなっているなんて…。
戸板に乗せられて、近所の診療所へ。医師は自分のベルトを抜いて、太ももの上部をきつく縛ってくれた。このとき初めて「あぁ私の足、千切れたんや」と気づいた。
病院での治療は、傷口に赤チンを塗って消毒するだけ。毎日消毒しなければ傷口がすぐに腐って、強烈な異臭とともにウジ虫がわいてしまう。
「一人娘がこんな姿になってしまって。できることなら代わってやりたい…」。祖母が泣いている。「おばあちゃん、泣かないで。足なんてすぐに生えてくるから」。

大阪空襲訴訟原告団
代表世話人 安野輝子さん
「足は生えてこなかった…」
足はもう生えてこないのだ、と知ったのは小学校に入ってから。雨が降れば母がおぶって学校へ。つらかったのは運動会と遠足。「みんな修学旅行や遠足の話で盛り上がるけど、私、一度も行ったことがないのよ」。
そんな安野さんの人生を支えたのが洋裁。家に閉じこもりがちだった少女時代、洋裁学校に行きたい一心で、なれない義足をはめて3年間通いつめた。汗で義足がすべり、接合部分の皮がむける。痛みで「もう歩きたくないと」幾度思ったことだろうか。
1972年、一つのニュースが目に留まる。「全国戦災傷害者連絡会が、戦時災害援護法を求める」という報道だ。軍人・軍属には補償があるのに、空襲で被災した民間人には何の補償もない。議員立法で「援護法」を作り、謝罪と補償を求めようというものだ。
安野さんたち被災者は18年間、国会に働きかけ、法律は18回上程された。しかし全て廃案または審議未了。
 前列、左から3番目が安野さん
前列、左から3番目が安野さん厚生省(当時)に行ったときのこと。空襲で顔面大やけどの小見山重吉さんが「防空壕に逃げたのですが、壕に焼夷弾が入ってきて大やけどを負ったのです」と証言。すると厚生大臣は「それは運が悪かったんですな」。やり取りを聞き「なんて冷たい政府なんだろう」と感じた。
「ワシら、やられ損やなぁ」。小見山さんのつぶやきが耳に残る。
国会も政府もダメ。こうなったら裁判しかない。こうして大阪空襲訴訟が始まった。
「私らが歩んできた悲惨な人生を歴史に残さないと、また同じこと、戦争が繰り返されてしまいます。政府に謝罪と賠償を求めて残りの人生、この裁判にかけたいと思います」。
 「大阪空襲訴訟を知っていますか」5人にプレゼント
「大阪空襲訴訟を知っていますか」5人にプレゼント ご希望の方は、最終頁記載のファックスかメールでお申し込みを。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。
A5版64頁
定価700円
発行 せせらぎ出版
TEL:06-6357-6916
